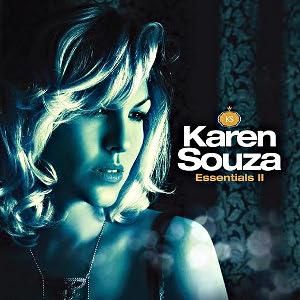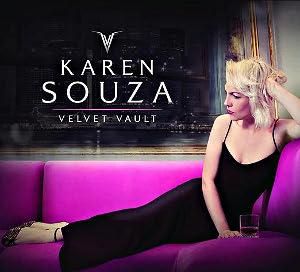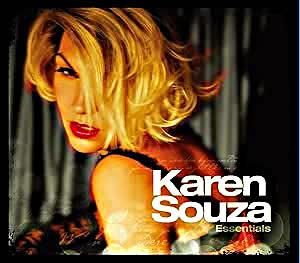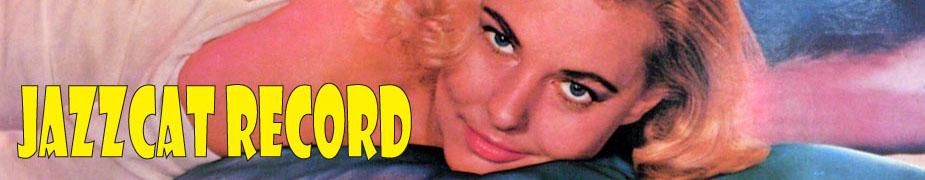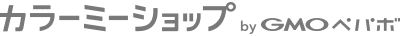2025年3月号
*粟村 政昭氏の著書「ジャズ・レコード・ブック」を読む。 連載
生前、ジャズ評論家の油井正一氏が、粟村政昭氏の「ジャズ・レコード・ブック」を世界最高の"ジャズ・レコードのガイド・ブック"として絶賛していた。ジャズ全般に渡るレコード・ガイド・ブックは例がない。1968年2月25日 第1刷発行、数年を経て2版〜3版と増補版が発売された。近年、多くのジャズ・ファンから再版の要請があり、一部の評論家やファンが尽力したが、再販は出来なかった状況があった。粟村氏が筆を起こしたのが1965年、58年の時を経て多くのファンの渇を癒すべく、ネットに依る復刻を思い至った。多くのジャズ・ファンや新たなジャズ・ファンの方々に、熟読玩味して頂けたらと思う。この著書は、雑誌「スイング・ジャーナル」1965年2月〜1967年8月まで連載された"ベスト・プレイャーズ
/ ベスト・レコード"に端を発し新たな人選の下、全面大改訂をほどこした書籍である。
今回「ジャズ・レコード・ブック」の前身の企画である、雑誌「スイング・ジャーナル」に、1965年2月〜1967年8月まで連載された、"ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード"に掲載された153名のアルバム紹介をまず読んで頂き、「ジャズ・レコード・ブック」に取り掛かることにしたいと思う。
********************
「 ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード 」
粟 村 政 昭
"ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード"は、雑誌「スイング・ジャーナル」1965年2月〜1967年8月まで連載された。最初の一年は編集部の人選であったが、1966年3月から粟村氏の人選に依る153名のレコード・ガイドである。
「某々のレコードは何を買うべきか」といった類の文章には年中お目にかかる様な気がするが、実際にレコードを購入するに当たって頼りになる内容のものは意外と少ない。その理由の第一は、撰択が甘くて最高点クラスのレコードと称するものがやたらと沢山並べられている場合が多いからだ。近頃の我国レコード市場は可成り乱戦気味だから、上手く立ち廻れば外国盤国内盤共に相当安い値段で購入することは出来る。しかし、千円、2千円の支出は我々の生活水準からみて、余程の金持ちでもない限り痛い事には変わりがない。そんな時に、これも良、あれも結構という大様な推薦のされ方をすると、全く腹が立つ。それに執筆者の中には妙にイキがって、ゲテ物レコードや道楽的な吹き込みを挙げる人もいるが、実際に身銭を切ってレコードを買うコレクターにとってこういう人々は明らかに敵である。そんな訳で、この稿を書くに当たってぼくは、推薦レコードは真に良いもの乃至は話題になったもののみにとどめ、出来るだけ少ない数のレコードを選出しておくことに決めた。勿論この他にも傑作佳作といわれるLPは沢山あるから、ファンの方はこの稿を一つの参考として、後は自分の好みに応じてコレクションの幅を拡げていかれるといいと思う。
第7回
< ダグ・ワトキンス >
早死に」したダグ・ワトキンスは全く惜しい人だったと思う。死んだら大抵の人は惜しんで貰える様だが、死者への敬意を抜きにしても、彼ほど秀れたリズムマンはそうザラに出て来ない様な気がする。彼が参加した録音の中で僕が一番印象に残ってレコードは、常識的に過ぎるチョイスかも知れないが、矢張りロリンズの名作「サキソフォン・コロサス」である。ロリンズの快演もさる事乍ら、フラナガン、ワトキンスといった驚異の新人達の登場は、当時のジャズ・ファンにとって嬉しいショックだった。ワトキンスはその後数多くのセッションに参加し、Transitionレーベルに自己名義の作品も残しているがさてどれが代表的好演」かと言われても難しく、皆「いつもの如く素晴らしい」という讃辞が適わしい演奏ばかりであった。
< ベン・ウェブスター >
ヴェテラン、ホーキンスが完全に老いぼれてしまった感が深いのに反して、ベン・ウェブスターの実力には未だ未だ見るべきものがある様だ。その昔エリントン楽団に在って吹き込んだ「Cotton
Tail」は今尚彼代表作として名高いが、こうしたアップ・テンポに於ける豪快なベンのプレイがファンの敬意を集めたのは精々スイング・イーラの終りまでで、それ以後の彼は年輪に物を言わせたOne
&Onlyのバラードの名手として、生存競争の激しい今日のジャズ界に見事に生き残って来た。彼のスロー物の中で僕が最高に買うのは、マーキューリー時代の物で、「You
Are My Thrill」、「Old Folks」ジョニー・オーティス楽団に客演して吹いた「Stardust」の三曲」はテナー吹奏史上永遠不滅の金字塔である。ヴァーブ入りしてからの彼は益々円熟して来た感じで、素晴らしい作品も沢山残しているが今では殆んど廃盤になってしまった様だ。中で僕はピータースン・トリオが付き合った「Soulville」を高く買っているのだが「Mulligan
Meets Webster」あたりも傑作の呼び声が高い。「Tenderly」で有名な「King of Tenors」も良いLPだが、合奏部にやや古めかしさを感じる。一頃ベンは表現がオーバァーに流れ、僕など「蒸気機関車が動き出したみたいだ」とか「プレス洩れを聞かせているのか音を聞かせてるのか判らぬなあ」などと悪態をついたものだったが、最近の彼はまた元の抑制された好ましい奏法に戻っているようだ。
< ランディ・ウエストン>
モンクの影響を巧みに消化したウエストンのピアノはデビュー当時から識者の注目を集めていたが、「Hi Fly」を代表作とする作曲家としての彼の才能も仲々どうして大したものである。彼は珍しく四分の三拍子を好み、「Little
Niles」、「At Five Spot」と次々に話題の作品を発表していったが、アフリカに関心を示し人種問題の闘士に変貌した頃から、大編成のいささかとっき難い作品を発表する事が多くなった。しかし近作「Randy!」(Bakton
1001)は所謂普通の概念で聴けるジャズであり彼の最高作と思われる力作である。
< ジョージ・ウェットリング >
ウェットリングはシカゴ派ドラマーの三羽烏の一人として、クルーパー タフ等と共に鳴らした人だが、他の二人が時代と共にスタイルを変えて行ったのに対し、彼自身あくまでもディキシー畑にとどまって活躍を続けて来た。デッカの「Chicago
Jazz Album」(8029)に収録された彼名義の数曲は名演として定評あるものだが、ウェットリングの最高傑作として自信をもって推せるのは、先般「エディ・コンドンの黄金時代」の片面として再発されたCollier'sJazz
Bandによる快演集であろう。これは一人ウェットリングの代表作のみならず、全ディキシーランド・ジャズのLP中でも優に上位を占め得るだけの名演である。
< クーティ・ウイリアムス >
クーティ・ウイリアムスをフィーチュアした、エリントン楽団の傑作「Concerto for Cootie」(「AT HIS VERY
BEST]Vic. LPM-1715に収録)は、あらゆるジャズ・レコードの中で僕が最も好きな演奏の一つだが、その他にも彼がエリントン楽団、グッドマン・セクステットやハンプトンのレコーディング・コンボに加わって残した傑作ソロは枚挙に暇がない位だ。エリントン時代のものは、わが国でも発売されて絶賛を博した「エリントンの黄金時代」の二組のセット物の中に沢山その優れたソロを聴くことが出来るが、BG時代の傑作は現在欧州盤に依る他は入手不可能である様だ。BGと共に録音したソロの中では「AS
LONG AS I LIVE」が傑出していた。往年のクーティはオープンで吹いた場合の方がより感動的であると評され、彼がミュートをつけて吹く機会の方が多いのを惜しむファンが多かったものだが、近年エリントン楽団に復帰してからの彼は、逆にその特異なワー・ワー・ミュートに依る音響効果として生きる道を見出しているかの様で、彼ほどの偉大なミュージシャンが何を吹いても皆同じという楽想の枯渇化にあえいでいる姿を見るのは本当に悲しい。ハンプトンと付き合った中では、豪放極まりない「RING
DEM BELLS」のソロを僕は買う。
次回につづく (参考文献 東亜音楽社)
=========================================================================================================================================

<<< コンポーネントステレオが欲しくなったきっかけについて >>>
 最初は兄が持っていたモノスピーカーの上にプレーヤーをおいて聴く電蓄?でメーカーは忘れてしまいましが、主にEP盤をかけて聴いていた。音の良し悪しなどではなく音楽を聴いて楽しんでいて最初に聴いたのはDECCA盤アームストロングの「黒い瞳」やマティー・ロビンス「ホワイト・スポーツ・コート」、(ちなみにマティーはJAZZのアルバムも出いる)、マントバーニー・オーケストラ、スタンリーブラック・オーケストラ、ロジャー・ウイリアムスのピアノなど兄が持っていた
最初は兄が持っていたモノスピーカーの上にプレーヤーをおいて聴く電蓄?でメーカーは忘れてしまいましが、主にEP盤をかけて聴いていた。音の良し悪しなどではなく音楽を聴いて楽しんでいて最初に聴いたのはDECCA盤アームストロングの「黒い瞳」やマティー・ロビンス「ホワイト・スポーツ・コート」、(ちなみにマティーはJAZZのアルバムも出いる)、マントバーニー・オーケストラ、スタンリーブラック・オーケストラ、ロジャー・ウイリアムスのピアノなど兄が持っていた レコード盤をかけて楽しんでいた。高校の時にコンソールステレオを買ってもらいアンプは真空管式で出力も6x6w、チューナー付きで今では考えられない再生音にエコーをかけるつまみがあり、プレーヤーは17cmのターンテーブル、レコード針はダイヤモント針でアームの頭に回転させつまみがありSP盤も聴けるようになっていた。当時はサファイア針も存在していました。ヘッドホーンを買って夜おそくまで聴けるようにしたのですがイヤホーンジャックなど付いていなかったので今ではどこに配線をしたかは覚えていませんが直接アンプにジャックケースの線をつないで聴いていた。FMは室内にT字アンテナをはっていましたが当然感度はあまり良く
た。レコードも自分の小遣いで買いはじめ当時はやっていたアメリカフォークソングのPPM、ジョーン・バエズ、ボブ・ディラン、オーケストラのマントバーニー、ピアノのロジャー・ウイリアムスなどを購入し聴いていた。
レコード盤をかけて楽しんでいた。高校の時にコンソールステレオを買ってもらいアンプは真空管式で出力も6x6w、チューナー付きで今では考えられない再生音にエコーをかけるつまみがあり、プレーヤーは17cmのターンテーブル、レコード針はダイヤモント針でアームの頭に回転させつまみがありSP盤も聴けるようになっていた。当時はサファイア針も存在していました。ヘッドホーンを買って夜おそくまで聴けるようにしたのですがイヤホーンジャックなど付いていなかったので今ではどこに配線をしたかは覚えていませんが直接アンプにジャックケースの線をつないで聴いていた。FMは室内にT字アンテナをはっていましたが当然感度はあまり良く
た。レコードも自分の小遣いで買いはじめ当時はやっていたアメリカフォークソングのPPM、ジョーン・バエズ、ボブ・ディラン、オーケストラのマントバーニー、ピアノのロジャー・ウイリアムスなどを購入し聴いていた。  春休み偶然に中学校時代の友人に出会い家に誘われて遊びに行ったのですが大変なカルチャーショックをうけた。友人はすでコンポーネントのステレオで、最初に聴かされたのがコルトレーンの「GIANTSTEPS」、ステレオでもショック、音楽でもショックを受け、弟が作ったという真空管アンプ(TRIOのキットW46K)で聴かされこれもショックで、その後は自分のステレオでは聴
春休み偶然に中学校時代の友人に出会い家に誘われて遊びに行ったのですが大変なカルチャーショックをうけた。友人はすでコンポーネントのステレオで、最初に聴かされたのがコルトレーンの「GIANTSTEPS」、ステレオでもショック、音楽でもショックを受け、弟が作ったという真空管アンプ(TRIOのキットW46K)で聴かされこれもショックで、その後は自分のステレオでは聴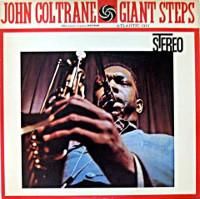
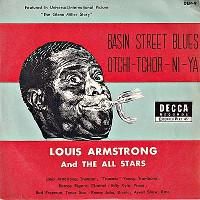 く気がなくなってしまい、なにか聴いている音楽も色あせてしまったものです。コンポはすぐには手に入りそうもないのでせめて聴くものを変えようと思いましたがすぐにJAZZだとちょっと抵抗があり、そこでクラシックを聴こうと思いお金を借りてLP30枚を購入し聴き始めまた。相変わらず週末になると友人宅でJAZZを聴かされ「MY
FAVORITE THINGS」、「GIANT STEPS」、「A LOVE SUPREME」などコルトレーンずけでした。夏休みに二人で川崎の三菱ふそう自動車にアルバイトに行くことになり私の目的はコンポネントステレオが欲しく、油で手はかぶれ、ズボンのベルトは剥がれるし食欲もおちきついアルバイトでしたが二か月間続けました。
く気がなくなってしまい、なにか聴いている音楽も色あせてしまったものです。コンポはすぐには手に入りそうもないのでせめて聴くものを変えようと思いましたがすぐにJAZZだとちょっと抵抗があり、そこでクラシックを聴こうと思いお金を借りてLP30枚を購入し聴き始めまた。相変わらず週末になると友人宅でJAZZを聴かされ「MY
FAVORITE THINGS」、「GIANT STEPS」、「A LOVE SUPREME」などコルトレーンずけでした。夏休みに二人で川崎の三菱ふそう自動車にアルバイトに行くことになり私の目的はコンポネントステレオが欲しく、油で手はかぶれ、ズボンのベルトは剥がれるし食欲もおちきついアルバイトでしたが二か月間続けました。
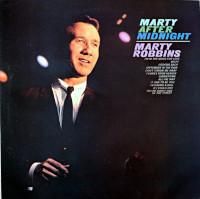
*** 次回は最初のコンポは何をそろえてについて
=========================================================================================
60年代以降活躍しているボーカリストを紹介します。
たくさんのボーカリストがでています。この時代公式サイト、facebookなどで
自身発信をしている人が多く時代はかわりました。
Karen Souza カレン・ソーザ
2010年にブルーノート東京でも出演し日本ビクターと契約している。ビリー・ホリディ、ペギー・リー、エラ・フィッツジェラルドなどの
影響を受けている。ヴァイオリンなどの楽器を取り入れ、彼女の世界を表現している。
発売CDの一部