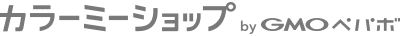JAZZCAT-RECORD メールマガジン 2023年12月号
【今回から連載で粟村正昭・著の「ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード」をとりあげます。】
第一回 < ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード 粟村正昭 著 >
"ベスト・プレイャーズ / ベスト・レコード"は、雑誌「スイング・ジャーナル」1965年2月〜1967年8月まで連載された。
最初の一年は編集部の人選であったが、1966年3月から粟村氏の人選に依る153名のレコード・ガイドである。「某々のレコードは何を買うべきか」といった類の文章には年中お目にかかる様な気がするが、実際にレコードを購入するに当たって頼りになる内容のものは.意外と少ない。その理由の第一は、撰択が甘くて最高点クラスのレコードと称するものがやたらと沢山並べられている場合が多いからだ。
近頃の我国レコード市場は可成り乱戦気味だから、上手く立ち廻れば外国盤国内盤共に相当安い値段で購入することは出来る。しかし、千円、2千円の支出は我々の生活水準からみて、余程の金持ちでもない限り痛い事には変わりがない。そんな時に、これも良、あれも結構という大様な推薦のされ方をすると、全く腹が立つ。それに執筆者の中には妙にイキがって、ゲテ物レコードや道楽的な吹き込みを挙げる人もいるが、実際に身銭を切ってレコードを買うコレクターにとってこういう人々は明らかに敵である。そんな訳で、この稿を書くに当たってぼくは、推薦レコードは真に良いもの乃至は話題になったもののみにとどめ、出来るだけ少ない数のレコードを選出しておくことに決めた。勿論この他にも傑作佳作といわれるLPは沢山あるから、ファンの方はこの稿を一つの参考として、後は自分の好みに応じてコレクションの幅を拡げていかれるといいと思う。
< キャノンボール・アダレイ >
モダン・ジャズ界の人気男キャノンボール・アダレの名を冠したLPはざっとカタログを見渡しただけでも20枚は下らないという賑やかさだがその中で僕が責任をもって推薦出来るLPと言え「SOMETHIN'ELSE」と「イン・シカゴ」の二枚だけだ。共に、キャノンボールのマイルス在籍時代の録音だが、前者に於けるキャノンボールのソロは締まりがないが、共演している親方のマイルスが誠に見事な出来栄えで、充分リラックスしていながら粗雑に走らず、数多いマイルスの傑作の中で最右翼の一作に数えてよい吹奏ぶりを示す。ハンクとサムの両ジョーンズ、アート・ブレイキーのドラムも誠に気持ちの良いクッションを送っている。従って推薦の意味は平均点と解して頂きたい。
マイルスの厳しい監督の下に於けるキャノンボールの精進振りは、マイルス名義の傑作「マイルス・トーン」と「カインド・オブ・ブルー」の二枚にも伺えるが、イン・シカゴはマイルスが抜けたマイルス・コンボの演奏で、ここでは完成途上にあるコルトレーンとキャノンボールの一騎打ちが凄まじいばかりの迫力をもって繰り広げられる。キャノンボールが、独立後に放ったベストセラー「イン・サンフランシスコ」は発表当時オーヴァー・ファンクだとかコマーシャルだとか言われて評判が悪かった。しかし今になって考えてみれば、多少の差こそあれ以後のキャノンボール・コンボの吹き込みはすべてこの線に沿って行われてきている訳で、僕としては発足当時のバンドの成否を賭けたこの第一作の熱演をリバーサイド盤中では一番高く買いたい気がしている。
< ルイ・アームストロング >
フレッチャー・ヘンダーソンやデューク・エリントンの再発物がどしどし世に出る現況にあって、米コロンビアに残された Armstrong Story 全4枚の傑作がまだ陽の目を見ないのを全くぼくは遺憾に思う。このことは、これまでに抜粋物を余り出し過ぎた関係で完全な物の発売が遅れているのかも知れないが、27,8年をピークとしたホット・ファイブ、ホット・セブンの熱演を納めたこれらのLPは、ひとりルイの傑作のみならず史上に輝く不滅の名盤である。一枚ずつ購入しょうとするファンには、ハインズと組んだVol.3 (Col,CL-853)を筆頭に、Vol.2の「Hot Seven」(852),Vol.1の「Hot Five」の順に買われることをお勧めする。戦後のオールスターズ時代のものでは、音が少し悪いがティーガーデンとの絶妙なコンビネーションの聞かれる「Town Hall Concert」(Vic.LPM-1433)が素晴らしく、「サッチモをあなたに」(Col.PMS-7/8)の中の一枚「W.C.ハンデイ集」は録音も良く、ルイの歌が最高の出来である。これらに続くものとしてはデッカの「シンフォニイ・ホール」(Dec.JDL-5016/7)と、ルイのオールスターズが最高のメンバーを揃えていた頃のスタジオ録音「N.O.Nights」(Dec-8329)「On Stage」(Dec-8330)が傑作だ。
< カウント・ベイシー >
「ベイシーの最高傑作は ? 」と聞かれれば、ぼくは一瞬の躊躇もなく「レスターが居た頃のデッカ盤」と答える。レスター・ヤング、ハーシャル・エバンス、バック・クレイトンといった名手を揃え、オールアメリカン・リズムセクションを擁した37,8年のこのバンドの偉容は「Best of Basie」(Dec.DX-170)の二枚のアルバムの中に余す所なく収録されている。当時としては珍しい位よくバランスのとれたこれらの録音に耳を傾けるならば、当時の真のスイング王がグッドマンにあらずしてベイシーであった事を誰しも疑わぬであろう。このLPは先日我国でも発売されたが、まことに遺憾な事に疑似ステレオ盤であった。 ジャズ録音史上最大のゲテ物はこの疑似ステレオなる代物と複合テープ録音だと思うが、20数年前の録音を何が何でも二つに分けて左右のスピーカーから聞かねばおさまらぬなどと言う風潮は笑止の限りである。従って正統派のコレクターには少し値は張るが自然な音に再生されている海外盤のモノーラルをお勧めしたい。このレコードを買った後で「では次には」と言われる方があれば、これもためらうことなく「LESTER YOUNG MEMORIAL ALBUM」(Epic SN-6031)を推薦する。
< アート・ブレイキー >
アート・ブレイキーは僕の最も好きなドラマーの1人である。但し僕の好きなブレイキーはリズムマン或いはリーダーとしての彼であってソロイストとしての演奏についてはそれ程でもない。秀でた新人の起用振り、独奏者のバックに付けていくリズムの変化とメリハリのはっきりした独自のアクセント、全く彼ぐらい豪放にみえてその実緻密なドラマーは数少ない。彼が率いるメッセンジャーズのLPの内傑作と召されるものは可成り多いが、第一期の代表作としては「SILVER & JAZZ MESSENGERS」(B.N 1518),「AT BOHEMIA VOL.1」(B.N 1507)の二枚を、第二期のものとしては「サンジェルマン」の第二集を、第三期の傑作としては「スリー・ブラインド・マイス」(U.A)と「BUHAINA'S DELIGHT」(B.N)を各々挙げておきたい。メッセンジャーズ以外のものの中では、ブラウン、シルバーの入った「AT BIRDLAND」が断然傑作。
モンクがモンクが客演した「モンクとブレイキーのジャズ・メッセンジャーズ」(Atl)も面白い。
< クリフォード・ブラウン >
ブラウンーローチのジャズ史に残る名コンビが残してきた名盤についてはこれまでに飽き飽きする程語られて来たので詳述は避けたい。彼らの傑作を最も経済的にコレクトするためには四枚のLPから選曲された「ベスト・オブ・ブラウン」(Ph)の二枚を買うのが一番いいだろう。これに「BEST OF BRWN & ROACH」(GNP)のコンサート録音を加えれば、ブラウン-ローチの遺産はほぼ完全に蒐集出来る。ブラウン個人のものでは前述したブレイキーとのセッションが圧巻でハンプトン楽団在籍中に巴里で秘密録音したLPも良かったが今は廃盤成っていてこれは全く残念だ。
< バック・クレイトン >
昨年3月、エディ・コンドン・オーケストラの一員として来日し、依然衰えぬ技巧を聴かせてくれたバック・クレイトンは、レスター・ヤングやハーシャル・エバンスと並ぶ全盛時代のカウント・ベイシー・バンドの花形奏者の一人だった。彼もまたルイ・アームストロングの影響を強く受けて育ったトランペッターであったが、ルイの持っていた華やかさとはおよそ縁遠い渋味の勝ったプレヤーで、それ故にこそ、その繊細な味が識者に認められ、余りの地味さの故にまた、一般の人気を博するまでに至らなかった。ベイシー時代に彼が残したプレイは「BEST OF BASIC」(Dec)の中に聴く事が出来るが、43年に入営の為退団。46年除隊してからはJATPに加わって一年半楽旅し、その後はヨーロッパに渡って活躍した。彼自身の名を冠したレコーディングの中で最も有名なものは、53年から数年間にわたって随時コロンビアに吹込まれた長時間のジャムセッション・シリーズ、その成果については長過ぎるとか、よくリラックスしているとか、賛否相半ばした。これらは現在皆廃盤に」なっているが、この中ではウディ・ハーマンの加わった「HOW HI THE FI」あたりが好評で、確かDB誌でも、五ッ星をとった。ヴァンガードが制作した一連の中間派セッションの中で、バックがルビイ・ブラフと渡り合った「BUCK MEETS RUBY」が秀れた出来だったが、これも今はカタログに残っていない。現在市場に出ているLPの中には残念ながら良いものが見当たらない。
< ナット・キング・コール >
ナット・コールは僕の最も好きなピアニストの一人だった。彼は先人のアール・ハインズ、後進のウイントン・ケリー同様、歯切れの良いタッチ、比類のないスイング感を持ち上品なユーモアと強力な左手を備えた稀に見る趣味の良いピアニストだった。ヴォーカリストとしての彼については今更多言は要すまい。トリオ時代に示した小粋な弾き語りから偉大なるポピュラー・シンガーとした晩年に至るまで、幾度かのスランプはあったが、強烈な個性に彩られた彼の唄声は、文字通り一世を風靡した。強烈な個性に彩られた彼の唄声は、文字通り一世を風靡した。ピアノと唄を含めて、ジャズマンとしてコールの真髄は、初期のデッカ盤「IN THE BEGINNING」(8260)キャピトルの「黄金のトリオ」の二枚のトリオ盤の中に燦然として輝いている。レスター・ヤングと共にアラディンやクレフに吹き込んだセッションやJATPのステージに於ける熱演はピアノストとしてのコールの力量をより明確に示した快作だったが、先般惜しくも廃盤になってしまった。
「アフター・ミッドナイト」は、ヒット・メイカーとして名を成してからのコールのジャズ物で、ゲスト・スターを迎えての円熟した彼の歌い振りは流石大スターとしての名に恥じない貫禄だった。彼の出世作となった「スイート・ローレン」は前記三枚のLP中に各々納められているが、この中一番有名なのはデッカ版で、オスカー・ムーアのギター・ソロも識者の注目を惹いた。ポピュラー物の中では「スターダスト」の入った「恋いこそすべて」が忘れられない。
< オーネット・コールマン >
モダン・ジャズの革命児オーネット・コールマンが、ヴァイオリン、トランペットといった新楽器をたずさえてジャズ界に復帰したという。しかも非常な好評を以って迎えられているらしい。ジャズ界の異端児と言われ、狂い咲き的な存在と目されていた彼が商業ベースに乗り切れずに引退してしまった後も、エリック・ドルフィー、セシル・テイラーをはじめとする後続前衛派達はたゆまぬ苦闘を続け、今日商業的には依然恵まれずとも、音楽的な意味で又数的な意味合いに於いて、前衛派は今やジャズ・シーンに於いて確たる一角を占めたかの感がある。オーネットのまいた一粒の麦は根強く育ったのである。総師コールマンのカンバックによって、今後の前衛派の活躍は益々注目すべきものになったと言える。コールマンがレコード界にデビューして吹き込んだ二枚のコンテンポラリー盤は、彼自身の未熟さと共演者に適材を得られなかった為もあって余り良い出来とは申せない。彼の名を一躍高からしめた「LONELY
WOMAN」は「SHAPE OF JAZZ TO COME」の中に納められているが、コールマンのLPの中で僕が最高に推すのは「オーネット!」である。これは彼の持つ自由奔放さが音楽的な成熟を倶って、見事に生かされた傑作である。「CHANGE OF THE CENTURY」がこれに次ぐ。「FREE JAZZ」はダブル・カルテットによるフリー・インプロビゼイションと言うジャズ史上かつてなき大胆不敵な試みを記録した大問題作だが、これを美とするか醜とするかには、極端な賛否両論があろう。「ジャズとはこういうもの」という既成小概念を以って聴いたのでは、「FREE JAZZ」がただの騒音にしか思えないのは確かだ。このレコードのジャケットが又まれにみるすばらしさで、この点でも問題作たるの名を恥ずかしめない。彼がテナーを吹いた「ON TENNER」もDB誌で5ッ星をとった。
< ジョン・コルトレーン >
マイルス・コンボに加入した頃のコルトレーンは誠に下手なテナーマンであったそうだ。初期の吹き込みレコードも、この事実を裏書きしている。しかしトレーンは今では伝説的となった猛練習に依って隠れていた自己の素質を十二分に開花させた。マイルス・コンボがプレスティジに録音した56年5月と10月の両セッションを聴けば、加速度的なトレーンの成長の早さに誰しも目を見張るであろう。アトランティックに吹き込んだ「GIANT STEPS」によって、コルトレーンは今日のあの吹きすさぶ熱風の様なテナー・スタイル完成への輝かしい第一歩を記した訳だが、それ以前の、うねうねと蛇の様に続いて行く長いフレーズとドライな、それでいて暖か味のある独自のトーンの方をより愛するファンも大勢ある。「GIANT STEPS」以前のレコードの中で僕が推薦したいと思う演奏は、歴史的なモンクとの顔合わせを」記録した「THELONIOUS MONK WITH JOHN COLTRANE」(RIVERSIDE)、マイルスやキャノンボールと共演した「モード・スタディ」、「キャノンボール・イン・シカゴ」、自己名義の「BLUE TRAIN」、「SOUL TRANE」、自己名義の「MY FAVORITE THINGS」、インパルス入りしてからは「インプレッションズ」、「コルトレーン」、「アフリカ・ブラス」はシネラマ版の猛獣映画を見ている様で僕は買わない。
< エディ・コンドン >
シカゴ・ジャズなる言葉は、いつの間にか本来の語義を離れて、コンドン一家の演じるディキシーランド・ジャズの代名詞と化した感があるが、これも言ってみれば、リーダー乃至はプロモーターとしてのコンドンの勢力の、しからしめる所であろう。コンドンは、メズロー、ティシュ、フリーマン、クルーパといったシカゴのジャズ青年達を率いて歴史に残る何曲かの名演を残したあと、次第に商業主義との結びつきを深めてコンドン・ジャズとでも称すべき味も素気もない安手のディキシー・ランド・ジャズの乱造を始めた。そこにはパナシェ達が、「シカゴ・スタイル」という特別な名称を捧げた頃の彼等独自の素朴にしてジャズ本来のスピリットに溢れた真摯な態度は概になく、魂の籠らぬソロが延々と続く場合が多かった。昨年来日した時のコンドンは「チンコロ伯父さん」然とした風貌でファンの好感を集めていたが、こんな所が案外、安い演奏を高く売るのに役立っていたのかも知れない。「シカゴ・スタイル」と讃えられた頃の彼等の録音を一枚にまとめたLPは今は無いが「JAZZ ODYSSEY VOL.2」(COLUMBIA C3L-32)の中に数曲納められている。
「シカゴからNYまで」(VICTOR)の片面は、コンドンがジャック・Tと顔を合わせた傑作集で、当時珍しかった白黒混成のセッションとしても高名。「CHICAGO JAZZ ALBUM」(DECCA)には39年吹込みの4曲が収録されているがこれも水準作。後年のものでは、やはりジャクスンと組んだデッカ盤が彼年の心意気のうかがえる力演だったが、現在は廃盤に成っている。コロンビアはコンドン・ジャズの在庫豊富だったが、ことごとく廃盤になっているのは意外。ヴァーブの新盤も好評だったが先般カタログから落ちてしまった。
次回につづく (参考文献 ?東亜音楽社)
=========================================================================================================================================
つまらないけど、おもしろい
Black & Blueはジャズとブルースを中心とするフランスのレーベルで、その数は膨大だ。ジャズではカンサスジャズやテキサステナーなど中間派スイングを基盤に、モダンにまで広がりがある。しかし、このレーベル自体の人気はイマイチで、あまり話題に上がることはない。ジャズ喫茶でも、ほとんどかかることはないようだ。膨大な作品があるのもかかわらず、あまり流通することもない不思議なレーベルである。流通しても決まったミュージシャンばかりで定番が多いのが現状だ。 たから、このレーベルの相対的なものが、なかなかつけめない。以前、ノーマからピアノトリオを中心に再発されたことがあるが、その時のジャケットはミュージシャンの顔が大きく写し出されたものが多く、どれもパットしないので、手を出す人は少なかったかもしれない。しかし、内容的には聴きやすく、スイング感に富んでいる。一応、3色刷りだがオリジナル仕様ではない。フランス・オリジナル盤の3色のジャケットになると色合いが良く、これぞBlack & Blue!と感じさせる鮮やかなものになる。また、フランス盤では再発されるとモノクロジャケットになったりするが、セピア色のもあるなど、どういう意図があるのか考えさせられる。そして、ライブ盤になると、これが実にカラフルなイラストぽいものレイアウトされている。されに、Midnight Slowsというシリーズがあるが、これはどれも女性のセミヌードばかり扱ったジャケットで、それを見る限りジャズのレコードとは思えないものだ。でもこのシリーズは、 PrestgeのMoodsvilleのようでムーディーなジャズを堪能できる。Buddy Tate, Arnett Cobb, Illinois Jacquet, Guy Lafitte, Eddie Daves,Cand Johnson etc錚々たるテーナーマンたちのバラードが味わい深き聴ける。
このレーベルのジャケットは、このようにある部分、シリーズ的な面で統一されたものになっている。膨大な量の中にはつまらないものもたくさんあるし、引きつけられるようなジャケットも少ないが、これだけ優れたものも隠れているので、想定外の内容で感動することが間々ある。他のレーベルには見られない、それを見つける一味違った面白さがBlack & Blueにはある。



=========================================================================================================================================
最近の新品レコードの価格は?
USAで流通しているレコードの新品価格を一部のせてみました。
OJCシリーズの180g盤が販売されています。
Bill Evans Sunday At The Village Vangurd $38.98
Kenny Burell To The ats $38.98
Bill Evans Waltz For Debby $38.98
Miles Davis Quintet $38.98
TheleNious Monk And John Coltrane $38.98
Mal Waldron Mal 2 $38.98
Duke Ellington & John Coltrane $38.98
ANALOGUE PRODUCTION で 180G $40.00 でています。
日本でも一部輸入されているものがありますが価格は7,000円以上が
ついてます。
">Relaxin' Wiht The Miles Davis Quintet(mono)
The Red Garland Quintet All Mornin' Long(mono)
Tommy Flanagan Overseas(mon)
Kenny Dorham Quiet Kenny(stereo)
Miles Davis Steamin' With The Miles Davis(mono)
Miles Davis Cokin' With The Miles Davis (mono)
Booke Ervin The Song Book(stere)
Benny Golson Groovin With Golson(stereo)
Eric Dolphy Out There(stereo)
Gene Ammons Nice(stereo)
========================================================================
たくさんのボーカリストがでています。
Carol Welsnan(キャロル・ウエルスマン)
カナダ生まれのジャズボーカリスト、ピアニストで自作の曲をアーチストにも提供していて
シンガーソングライターとして活動してた。
1995年ころからジャズのアルバムも出し、2007年以降コンスタントにアルバムを
発表。バークリーでピアノ演奏を学んだ。
発売CDの一部です。




=========================== 2023年12月号 ===================================================